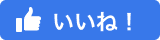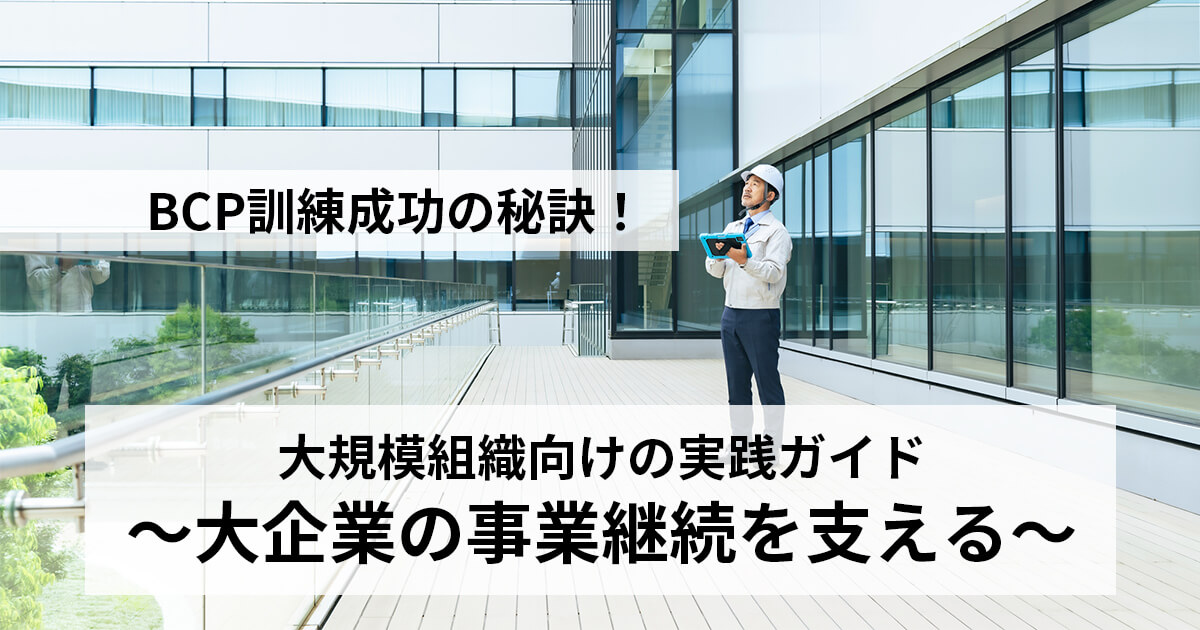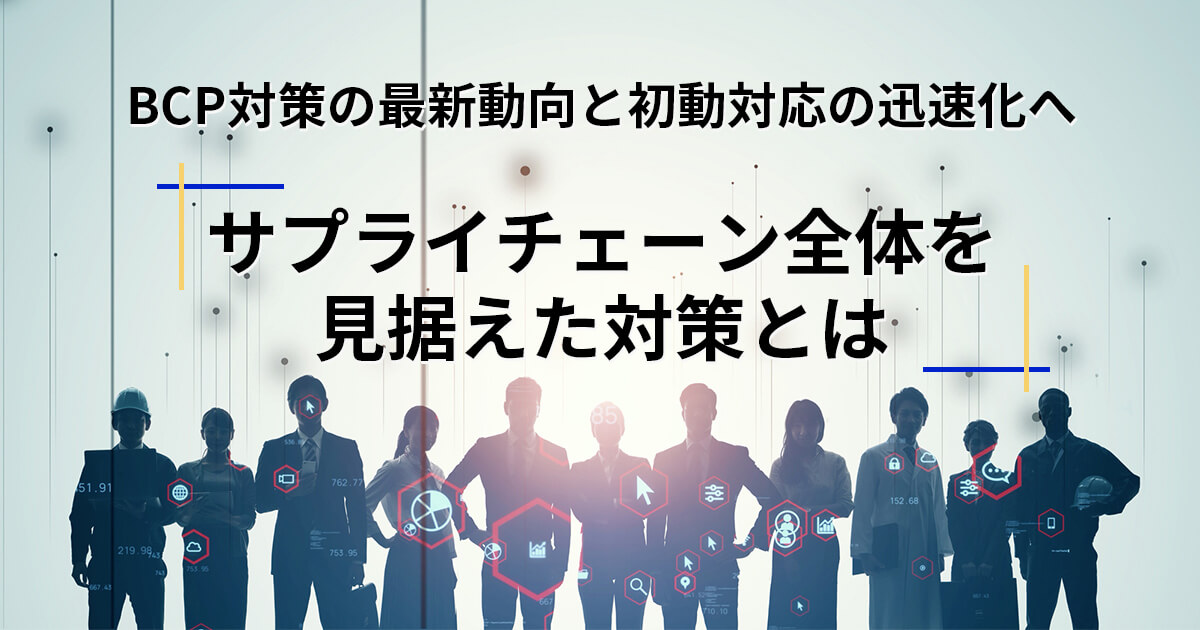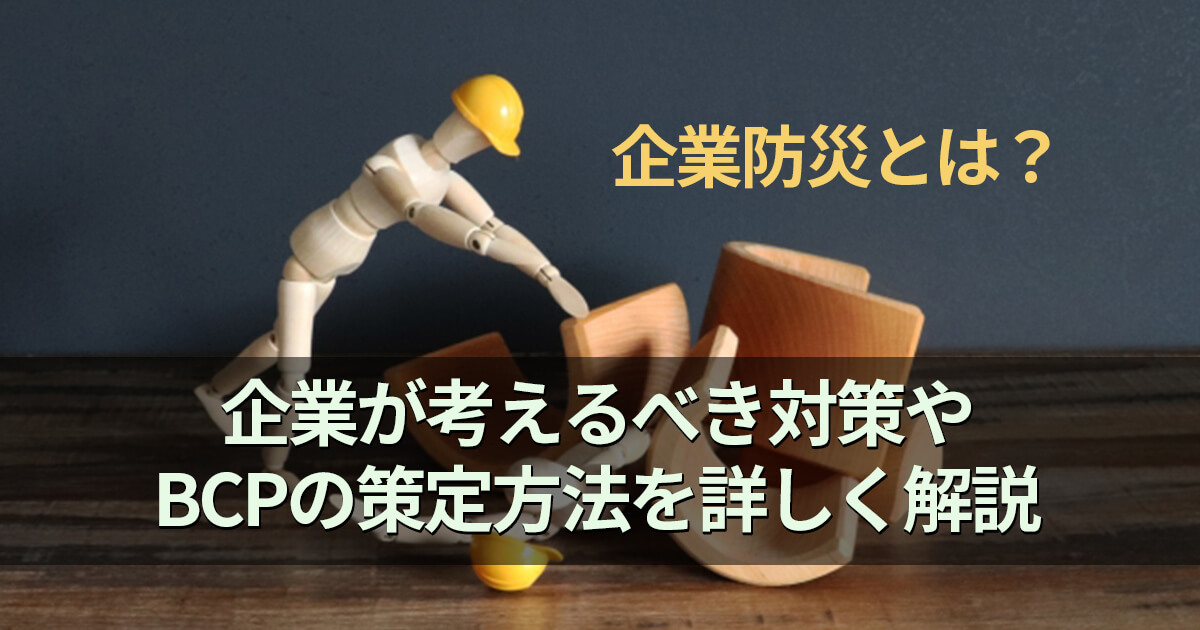目次
地震などの災害が起きた際、企業には従業員の安否を確認する義務があります。しかし大規模な災害が発生した際、通信障害などでスムーズに安否確認ができない可能性も考えられます。迅速に情報の収集や管理を行うため、あらかじめ安否確認の方法を定めておくことが重要です。
この記事では企業向けの安否確認方法を詳しく解説します。あわせて個人向けに家族の安否を確認する方法もまとめたので、参考にしてください。
企業における災害時安否確認方法
災害が起きた際、企業には従業員の安否確認を行う義務があります。その代表的な方法として、電話、メール、安否確認システムの違いを解説します。メリットとデメリットにも触れるので、導入の際の参考にしてください。
安否確認システム
安否確認システムは従業員に安否確認の連絡を一斉に行えるうえ、従業員の回答を自動で集計できるツールで、近年導入が進んでいます。従業員からの返答がない場合、自動で繰り返し安否確認を行えるため、担当者の負担をさらに減らせるというメリットがあります。
安否確認システムを選ぶ際は、メール以外にもアプリや電話の自動音声などさまざまな手段に対応できるシステムを選びましょう。従業員が回答しやすい方法、タイミングで返信できるため、回答率が高まります。
デメリットとしては導入費用がかかる点です。しかしデメリットを上回るメリットが多く存在するため、迅速に安否確認を行いたい企業は、まず安否確認システムの導入を検討すると良いでしょう。
安否確認システム「エマージェンシーコール ライトプラン」の詳細はこちら
電話
電話を使って安否確認をする場合は、各社員の連絡先へ直接架電する方法が一般的です。そのため各自の連絡先や「誰が誰に連絡するか」などの方法をまとめた緊急連絡網を事前に作成しておく必要があります。
電話での安否確認は、使い慣れているツールで個別の状況を詳細に確認できるメリットがある一方で、管理の手間がデメリットです。担当者が従業員の情報をまとめる際にかなりの時間や労力がかかります。また、災害時に回線が混雑し、電話がつながらないなどの可能性も考えられます。
メール
企業の独自ドメインのメールや、Gmailなどのメールサービスを使っての安否確認は電話と同様、簡単に取り入れられる方法です。メールの場合は、メーリングリストを使った一斉送信が可能なため、ひとりずつに電話をかける方法に比べ、手間が省けるといえます。
しかし災害時の通信障害によりメールが届かなかったり、遅延が起きたりする可能性が考えられます。返信内容の確認と集計にも時間を要するため、従業員の多い企業や事業所では迅速な対応につなげられません。
上記のように電話やメールは災害時に繋がらないケースが多くあります。確実に従業員の安否確認を行うには、災害時に強い安否確認システムの導入がおすすめです。
災害時には安否確認システムの導入がおすすめ
企業が従業員に安否確認を行う際は、電話やメールよりもセキュリティ面で安心できる安否確認システムを使うのがおすすめです。推奨する理由を詳しく解説します。
管理の負担を軽減できる
担当者の負担を減らしたい企業には、安否確認システムの導入がおすすめです。安否確認システムには地震の震度に対応した自動送信や、回答の自動集計などの機能があるため、管理にかかる手間や時間を大幅に削減できます。さらに安否確認メールのテンプレートが用意されており、事前準備も簡単です。
自動集計の機能では、従業員がメールに記載されているURLなどにアクセスし、専用ページで回答した内容をリアルタイムで集計します。回答者数などが数値で出るため、状況を即座に把握できます。また、部署ごとや出社が可能な従業員など条件に合ったデータの抽出が可能で、事業継続のための行動指示など次の対応にも活かせます。
BCP(事業継続計画)の策定に重要
大規模な災害やシステム障害などの緊急事態に、早急に事業の復旧や再開を実現するため、各企業でBCP(事業継続計画)の策定が求められています。特に従業員の状況を把握できる安否確認は、緊急時における初動対応の要です。そのためBCP(事業継続計画)を策定する際は、安否確認の方法をしっかりと定め、そこから事業の継続や復旧につなげるプロセスを構築することが重要です。
安否確認の回答率を高めるには、従業員に対する事前の教育や研修も鍵となります。従業員に安否確認の重要性を周知したり、実際の災害を想定して安否確認の訓練を実施したりなど、事前の対策を怠らないようにしましょう。
安否確認システム「エマージェンシーコール ライトプラン」の詳細はこちら
家族の災害時安否確認方法
次にご家庭で安否確認をする方法を紹介します。サービスやアプリなどさまざまな手段を紹介するので、各ご家庭で使いやすいものをセレクトしつつ、事前に約束事を家族間で共有しておきましょう。
災害用伝言ダイヤル(171)
災害用伝言ダイヤル(171)とはNTTコミュニケーションズらが提供する、電話の伝言サービスです。録音時間はひとつの伝言につき30秒で、ひとつの電話番号あたり20伝言まで録音できます。使い方は以下のとおりです。
【録音方法】
- 171に電話をかける
- 「1」を押して音声を録音する
(録音し直す場合は「8」を押す)
【再生方法】
- 171に電話をかける
- 「2」を押した後、伝言を聞きたい方の電話番号を入力する
- 録音された音声が流れる
(「8」を押すと伝言が繰り返される)
上記のサービスは固定電話や携帯電話、PHSなどで利用できます。災害時に備えて、あらかじめ安否確認を行うための電話番号を共有しておきましょう。
災害用伝言板(web171)
災害用伝言板(web171)は災害時に通信障害などが起きた際に、スムーズに安否確認できるインターネット上の伝言サービスです。携帯電話やPHSから、災害用伝言板(web171)にアクセスすることで、伝言の登録および確認ができます。使い方は以下のとおりです。
【登録方法】
- web171の専用サイトにアクセスする
- 伝言を登録したい電話番号を入力する
- 安否状況についてチェックを入れ、名前・伝言を入力する
- 登録ボタンを押して完了
【確認方法】
- web171の専用サイトにアクセスする
- 伝言を確認したい電話番号を入力する
- 登録された伝言が表示される
(確認後にこちらからの伝言を登録可能)
登録できる伝言は、ひとつの電話番号につき20個までです。ひとつあたり全角100文字まで伝言を登録できます。
災害用伝言板サービス
以下の通信会社でも、伝言サービスを提供しています。
いずれも各社の専用サイトにアクセスし、伝言を登録できます。他社の携帯電話やパソコンなどからも伝言を確認でき、さらに通信会社によっては伝言を届けたい相手のEメールアドレスに通知の送信が可能です。登録できる件数や文字数は通信会社ごとに異なります。
通常、災害時でないとこれらのサービスは利用できませんが、毎月1日・15日や防災週間などにお試しできるサービス期間が設けられています。 いざというときに慌てないためにも、あらかじめサービスを体験しておきましょう。
SNS
InstagramやTwitter、Facebook、mixiなどで発信すれば、SNS上でつながりのある方を中心に、より多くの人へ自身の安否状況を一括で知らせることができます。個別やグループにメッセージを送れる、DM(ダイレクトメッセージ)の機能も活用しましょう。
防災アプリ
防災アプリのなかには、安否確認機能が備わっているサービスがあります。たとえば「東京都防災アプリ」ならば安否確認以外に、特別警報や防災情報の受信、避難シミュレーションなどさまざまな機能があり、災害の備えとして役立ちます。
ただし家族間で安否確認を行うには、全員が同じアプリをあらかじめインストールしておかなければなりません。緊急時にスムーズに使えるよう、家族間で使い方をおさらいしておくとより安心です。
勤務先の安否確認システム
企業で導入できる安否確認システムのなかには、従業員とその家族同士で安否確認ができる機能を備えたシステムがあります。
たとえば「エマージェンシーコール」では、標準機能として家族向けの伝言サービスが備わっています。音声と文字でそれぞれ登録でき、メッセージのやり取りも可能です。2拠点にあるデータセンターが同時に稼働するため、緊急時でも安定してサービスが提供されます。東日本大震災や熊本地震でも稼働実績のあるシステムです。
従業員の安否状況の確認に加え、従業員とその家族の安否確認に役立てたい企業はぜひ導入を検討してみてください。詳細は下記サイトより確認できます。